モリンガの焙煎はお茶の製造工場でプロの技術により配合される

モリンガの焙煎は、品質がトップクラスのお茶の製造工場で行います。モリンガファームによるていねいな作業で乾燥・殺菌されたモリンガがお茶のプロのもとに委ねられる段階です。
※モリンガの乾燥工程については、こちらの記事を参考にしてください。
※乾燥の工程を終えたモリンガの殺菌については、こちらで詳しく解説しています。
モリンガは、モリンガファームのモリンガ研究所やワダツミ農園株式会社により収穫、乾燥、選別、殺菌という工程をたどってきます。ここからの工程は、岩手県一関市と福岡県宮若市に工場を構える株式会社精茶百年本舗のお茶を焙煎する技術によるものです。
本記事では、モリンガの焙煎についてお茶のプロである製造工場での取り組みを解説します。この段階から、モリンガはお茶のように焙煎され、さらに摂取しやすくなります。
モリンガを焙煎する

お茶の製造工場である株式会社精茶百年本舗では、モリンガを焙煎して素材の風味の良さを引き立てます。
焙煎によるメリット
焙煎によって得られるメリットは、原料を焙煎することで風味の引き立てだけではなく、香りも豊かに仕上げられる点ではないでしょうか。株式会社精茶百年本舗では、緑茶を焙煎する技術により、モリンガのような「葉物」の原料を低温でじっくり時間をかけて手掛けます。
この技術は、株式会社精茶百年本舗の独自製品「百年茶」の製造経験を反映したものです。
※参照元:株式会社精茶百年本舗「平泉 百年の郷|百年茶を知る」
プロが焙煎で注意していること
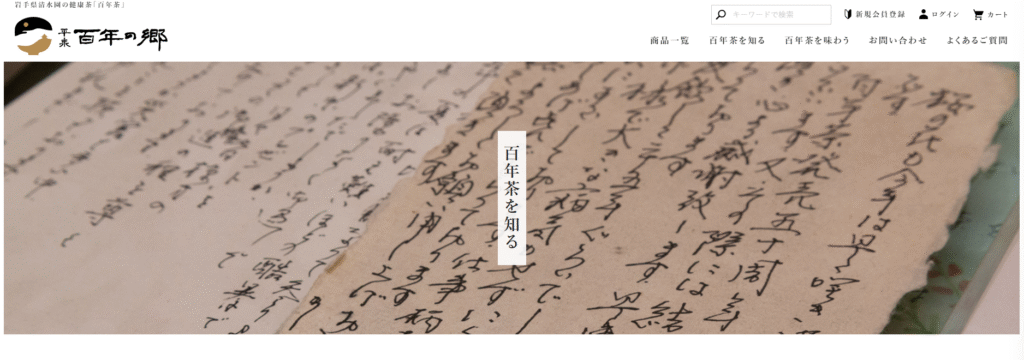
株式会社精茶百年本舗では、焙煎をするうえで温度管理に注意しています。「葉物」の焙煎は、焦がした場合、風味が損なわれます。そのため、焙煎作業は経験を積んだ焙煎士により行われるとのことです。
焙煎士の経験は、試行錯誤の結果身につけた品質を保つための重要なポイントになるでしょう。
※画像引用・参照元:株式会社精茶百年本舗「平泉 百年の郷|百年茶を知る」
また、焙煎は焙煎士の判断がさまざまな風味をつくり上げると考えられます。まさに焙煎は、味の決め手です。モリンガを焙煎するうえでも、焙煎時間や焙煎士の経験が重要な役割を果たします。
※参考:農林水産省「お茶づくりの1年|お茶畑から美味しいお茶が届くまで」
モリンガは焙煎により親しみが込められる

モリンガは、九州地方の地元農家(モリンガ研究所・ワダツミ農園株式会社)の方の手により、ていねいに育てられ収穫されます。
収穫したモリンガは、農家の方の手作業により異物を取り除く選別が行われます。その上で、乾燥させ安心安全に向けた殺菌処理が施される流れです。
今回は、モリンガ農家の方が手掛けてきたモリンガをお茶の専門家である株式会社精茶百年本舗の焙煎士の技術を施す工程について解説しました。
モリンガが家庭に届くまでは、原料の殺菌作業のあとでも、プロの技術が必要な焙煎作業が行われます。モリンガは、「ここまで手を掛けているのか」という入念な工程を経て、品質の良さを守っている印象です。
なぜ、モリンガの焙煎が必要なのか?その理由

モリンガの焙煎は、その後工程となる「ブレンド」に欠かせません。なぜ、モリンガに焙煎が必要な理由は、風味をより豊かにすることや、豊富な栄養素に良質なたんぱく質を追加することです。
モリンガ単体の味では、ワサビノキ科の香味植物として料理のアクセントになります。しかし、毎日摂取する野菜としては、独特な風味をよりさっぱりとまろやかにする必要があります。
そこで、今回紹介している九州のモリンガ農家2社と精茶会社の協力により、モリンガに大豆イソフラボンを含めたプロテインの開発に取り組みました。もともと90種類以上の豊富な栄養成分を含むモリンガに良質なたんぱく源となる大豆イソフラボンを含め、さらに飲みやすく「抹茶」と「ほうじ茶」のフレーバーで分類しています。
※モリンガの栄養成分については「モリンガの栄養価」でくわしく解説しています。
目覚めにさっぱりしたいときは、抹茶味。落ち着いたひとときに、まろやかな味を楽しみたいときはほうじ茶味がおすすめです。MORISOY(モリソイ)は、焙煎したモリンガをより日常生活の食習慣に取り込められるように工夫されました。
MORISOY公式 EC サイトはこちら
MORISOYをAmazon でご購入の場合はこちら





