植物としてのモリンガ|亜熱帯性の地域限定で育つ濃い緑のワサビノキ

”モリンガ”と聞いて、実際の木や葉などを想像できる人は多くないでしょう。どちらかいうと、このページでは、植物としてのモリンガについて、育つための特徴を解説します。
モリンガはワサビノキ科の植物

モリンガは、ワサビノキと言っても、お寿司に欠かせない「わさび」とは異なるものです。ワサビノキと呼ばれる理由は、モリンガの根に香味があるからといわれています。
※出典:厚生労働省「Moringa oleifera(いわゆるモリンガ、ワサビノキ※)について」
ワサビノキについて詳細はこちらで解説しています。
モリンガは亜熱帯性の植物

モリンガは、暖かい地域で育つ植物です。気温が極端に低くなり湿気の多い地域では栽培できないと言われています。
モリンガを栽培するモリンガ研究所(福岡県久留米市)や、ワダツミ農園(鹿児島県肝属郡錦江町)は、モリンガ発祥の地である北インドと同じ緯度に位置しています。そのため、モリンガに最適な気候としてモリンガが育つための環境条件が整っているという強みがありますね。
亜熱帯性

亜熱帯性(緯度が25度から30度の地域)の気候の地域は、気温20度以上の月が4カ月〜8カ月あるといいます。
モリンガは、九州方面の一部地域・沖縄周辺において、栽培しやすさが原産国の北インド地方に近い暖かい気候の地域限定の直物です。
インドから日本に渡ってきたモリンガ
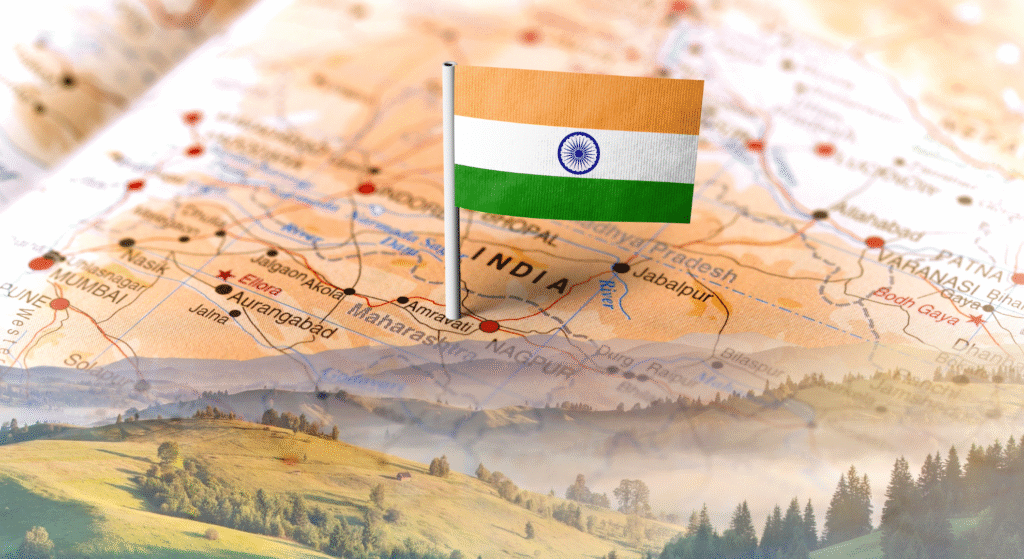
モリンガは、インド原産の熱帯早生樹(熱帯地域で早く成長する樹種)といわれています。いまでは、世界各国で栽培されています。原産国のインドに似た気候であれば、栽培できる植物です。
先ほども触れましたが、モリンガを栽培している地域は日本の一部地域(九州・沖縄の亜熱帯性気候地域)だけではありません。代表的な栽培地域は次の通りです。
- インド(原産国)
- アフリカ
- 東南アジア
- 中南米
- 日本(沖縄県、福岡県、鹿児島県、熊本県など)
※参考:林野庁ホームページ「近畿中国森林管理局における早生樹造林の取組 – 林野庁」
※出典:農林水産省「選定企業②:Moringa Moçanbique, Lda|4.1 企業概要」
モリンガの正式名称

植物としてのモリンガには、正式名称があります。農林水産省によると、次の学名と和名(日本での呼び名)が示されています。
学名:Moringa olefera
和名:ワサビノキ
※出典:農林水産省「選定企業②:Moringa Moçanbique, Lda|4.1 企業概要」
モリンガの木についての特徴

モリンガを丹念に育てているモリンガ研究所やワダツミ農園では、モリンガの大きな特徴を次のように表現しています。
モリンガの木

モリンガの木は、成長の速さが特徴です。約4カ月の期間で4〜5mほど成長します。また、二酸化炭素吸収能力が高く、CO2を減らす役割も担っている特徴が地球環境に役立っている印象です。
モリンガの成長する速度は、とてつもないパワーを秘めている木という特徴に匹敵します。亜熱帯性の地域では、ビニルハウス内の栽培でモリンガが一年中生えているとのことです。
モリンガの種

モリンガの種には、見た目に特徴があります。モリンガの種を初めて見る人は、毛の生えた感じにびっくりするでしょう。モリンガの種は食べられます。1さやに21個ぐらい入っていて、食べると苦くて渋い味がします。ただし、モリンガの種を食べたあとに飲む水は美味しく感じるでしょう。
モリンガの種は、温度の低い日本の気候では種の収穫が難しく、九州や沖縄など一定の地域と栽培経験が必要になると考えられます。
モリンガの葉

モリンガの葉は、鮮やかな濃い緑色で見た目は小さく、香りがしない点が特徴です。食感は、和名がワサビノキというだけに、噛むとワサビのようなピリッとした感じがします。ピリッとする食感は、サラダに入れて生で食べてもアクセントになります。
モリンガを育てている農家からのメッセージ

福岡県久留米市や鹿児島県肝属郡錦江町の地域では、モリンガの栽培が続いています。モリンガを栽培する農家では、モリンガのことを「手のかかる子ども」という表現をしています。

福岡県久留米市のモリンガ研究所では、モリンガの栽培を始めて10年経過しました。その経験から、発芽した際は、「除草が非常に大事」といわれています。モリンガの栽培のポイントは、「除草しないと厳しい」というメッセージをいただきました。

また、鹿児島県肝属郡錦江町のワダツミ農園では、インドから日本の地に来たモリンガのことを「よくぞ鹿児島に来てくれた」と感謝の意をあらわしています。
モリンガは、栽培に手間がかかる部分も含めて、「人に伝道していく役目」という意気込みの基盤となっています。





